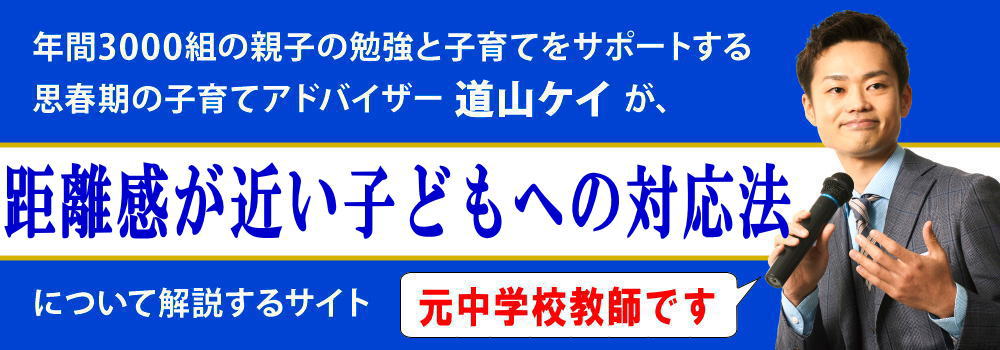距離感が近い子どもへの対応を知りたい方へ

距離感が近い子どもに関するページ内容
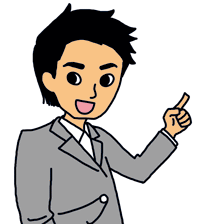
距離感が近い発達障害の子どもへの教え方
について解説します。
自閉症スペクトラムなど、
特に発達障害の子どもの中には、
物理的・心理的な距離感の取り方に
独特の特性を持つ場合があります。
過度に接近してくる場合や
コミュニケーションの取り方が
独特な子どもへの適切な関わり方を
元教師の経験からまとめました。
一人ひとりの特性を尊重しながら、
効果的な支援方法を実践することで、
子どもたちの学びや成長を
サポートすることができます。
目次
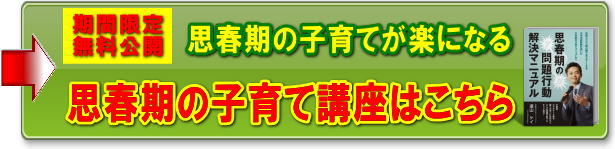
距離感が近い子どもの特徴と発達障害との関連性

距離感が近い子どもには、
どんな特徴があるのでしょうか。
主に3つのパターンがあります。
お子さんがこれらに当てはまるか、
チェックしてみましょう。
物理的な距離が近すぎる
会話するときに、
相手との距離が極端に近い子どもがいます。
一般的に友人同士の適切な距離は、
約1〜1.5メートルと言われています。
これよりも明らかに近い位置で話そうとする場合、
距離感が近いといえるでしょう。
相手が不快に感じていなければ、問題ありません。
しかし、嫌がられる原因になることもあります。
初対面でも体に触れる
物理的な距離だけでなく、心理的な距離感も重要です。
初めて会った人の肩をポンと叩いたり、
腕を触ったりする行動は、
慣れ慣れしいと思われることがあります。
親しい間柄なら問題ないことも、
初対面では相手を不快にさせる可能性があるのです。
プライベートな質問を急にする
人間関係では、
会話の内容も徐々に深まっていくものです。
最初は「どこの学校?」「何部に入るの?」
といった一般的な話題から始まります。
しかし、いきなり「好きな人は?」
などのプライベートな質問をすると、
相手は戸惑うことがあります。
これも心理的な距離が近いケースです。
これらの3つの特徴がある子は、
「距離感が近すぎる」と感じられやすくなります。
また、極端にこれらの特徴が見られる場合、
自閉症スペクトラムなどの
発達障害の可能性もあるでしょう。
自閉症スペクトラムの子どもにも効果的な3つの教え方

距離感が近い子供の場合、
親がサポートすることで、
改善できます。
では、どのように進めればいいのか。
自閉症スペクトラムなどの
発達障害の子供にも効果的な、
3ステップを紹介しましょう。
一度試してみてください。
ステップ①視覚的に距離感を伝える
言葉で「もう少し距離を取りなさい」と言っても、
どれくらいが適切なのかわかりません。
そのため、床にテープを貼って
「ここくらいの距離だよ」と示すと効果的です。
発達障害の有無にかかわらず、
視覚的な手がかりがあると理解しやすいものです。
子どもと一緒に練習する時間を作りましょう。
ステップ②具体的に説明する
心理的な距離が近い場合、
「いきなりプライベートな質問はやめな」
と言っても理解できません。そうではなく、
「好きな人を聞くのは1か月たってからね」
「友達の肩をたたくのは、相手にたたかれてからにしよう」
など、具体的に説明したほうが伝わりやすくなります。
あいまいな表現はやめましょう。
ステップ③プラスの声かけで練習する
練習を重ねるときは、
ポジティブな声かけを心がけましょう。
「また近すぎる!」と責めるのではなく、
「昨日よりずいぶん良くなったね」
「今日は意識できていたね」と褒めるほうがいいです。
小さな進歩を認めることで、
子どもは自信を持って取り組めるようになるでしょう。
自閉症スペクトラムなどの
発達障害の有無に関わらず、
子どもの距離感が近いと感じる場合は、
この3ステップを実践してみてください。
ルールを理解しやすくなるため、
実際の行動にも結びつきやすくなるでしょう。
専門家と一緒にできる2つのアプローチ方法
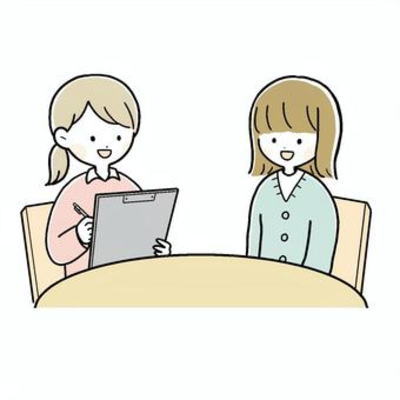
とはいえ、相手との心の距離感や、
どんな順番で話せばよいかなど、
家庭だけでは伝えるのが
難しいことってあるでしょう。
特に発達障害の子供は、
その傾向が強いです。こうした場合は、
専門家の力を借りるのも
一つの方法です。
公認心理師などの専門家と一緒に取り組むことで、
子どもが安心して練習できる環境をつくることができます。
よく行われているアプローチ方法は、次の2つです。
「ソーシャルスキルトレーニング(SST)」
1つ目は
「ソーシャルスキルトレーニング(SST)」です。
少人数のグループで、相手との適切な距離感や
言葉のやり取りを学ぶことができます。
専門家がサポートすることで、
子どもにとっても取り組みやすくなるでしょう。
気持ちを理解させるアプローチ
2つ目は「気持ちを理解させるアプローチ」です。
子どもに「こういうことを言われたら、
相手はどんな気持ちになるかな?」と質問することで、
少しずつ感情への理解を促していくことができます。
これらの方法は、専門的な知識があったほうがうまくいきます。
そのため、公認心理師などの
専門家にサポートしてもらうのがおすすめです。
学校と連携し、距離感が近いことで起こるトラブルを防ごう

思春期の子どもにとって、
友達関係は重要です。
しかし、距離が近すぎることで、
友達から嫌がられたり、
いじめのきっかけになったりすることが
あります。
だからこそ、
学校の先生と上手に連携していくことが大切です。
たとえば、先生には
「うちの子は曖昧な表現が理解できないため、
具体的な数字で伝えてもらえると助かります」
と伝えておくといいでしょう。
「距離が近いよ」ではなく
「1メートルはあけてね」というように、
数字で具体的に伝えてもらえると、
子どもも理解しやすいからです。
事前にこう言ったお願いをしておくだけで、
友達とのトラブルを防ぐことができます。
また、席の位置がきっかけで
トラブルになることもあるでしょう。
その場合は、できる範囲でいいので、
先生に配慮をお願いしておくといいです。
生徒の中には「ちょっと近いよ」と
やさしく教えてくれる子もいますが、
そうでない場合もあります。
小さな行き違いからケンカにならないよう、
あらかじめ対策しておくことが大切です。
もし発達障害の診断がある場合は、
それも学校に伝えておきましょう。
診断があると、
先生もより適切に対応しやすくなります。
伝えることで、子どもが安心して
学校生活を送れる環境づくりにつながります。
小中学生の子育ての悩みを解決するための重要なこと
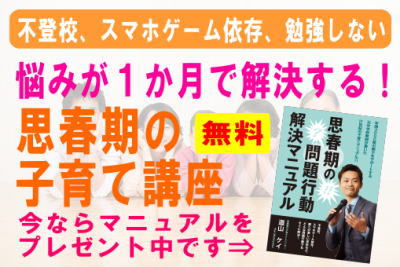
ここまでお伝えした内容を踏まえ、
子どもへ適切な距離感を伝えていきましょう。
しかし、
- できることはやっているはず
- なのに状況が良くならない
- 毎日イライラして子育てが辛い
このような状況になっていないでしょうか?
発達障害の有無に関わらず、
思春期には、不登校や非行、いじめなどの
問題行動が起こりやすくなります。
どう対応したらいいかわからない状態と
なることもあるでしょう。
そこで現在私は「思春期の子育て講座」を
無料で配信しています。ここでは、
- 思春期の子どもの気持ちと接し方
- 学校で問題を起こした時の対応法
- 不登校や引きこもりの解決法
- ADHDなど発達障害の子どもへの向き合い方
など、思春期の子どもを持つ親に
読んでいただきたい内容を、
詳しくお伝えしています。
思春期の特徴を知り、
対応方法を間違えないことが、
子どもと向き合う上で大切です。
正しく向き合えば、
親子関係が良くなり、会話が増えます。
子どもに伝えたいことを、
伝えられる環境ができるでしょう。
親であるあなたも、イライラが減るはずです。
今なら、3980円で販売していた
「思春期の問題行動解決マニュアル」を
受講特典としてプレゼントしています。
よろしければ、読んでみてください。
※のべ5万人以上が受講し、PTA講演会でも話している内容です。
動画で解説!!距離感が近い子どもへの対応法の詳細編