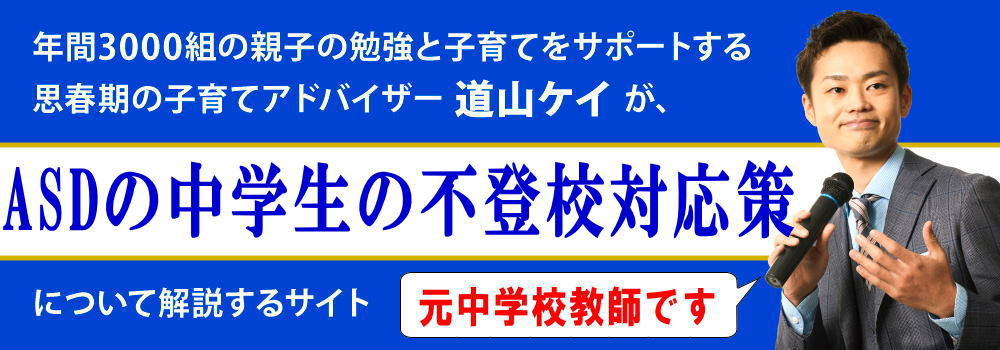ASDの中学生が不登校になったときの対応を知りたい方へ

ASD中学生の不登校に関するページ内容
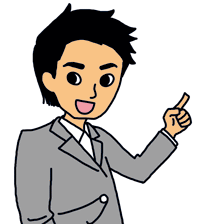
ASDの中学生が不登校になった時の対応について
解説します。
自閉症スペクトラム障害のある
中学生が学校に行けなくなった時、
勉強や友達関係について
どう支援すればよいか悩みますよね。
実はこれ、
特性を理解した対応が重要です!
ASDの特性を踏まえた不登校への対応と
家庭での勉強の進め方を
元教師の経験からまとめました。
適切なサポートをすることで、
子どもの状況に合わせた学習環境を整え、
将来への道筋を作ることができるはずです。
目次
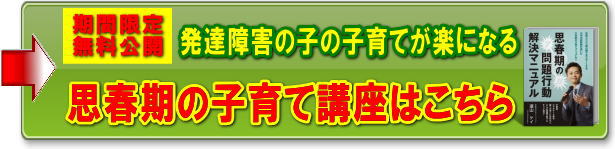
ASDの中学生が不登校になりやすい3つの理由

ASD(自閉スペクトラム症)の
特性がある子どもは、
不登校になりやすいといわれています。
なぜでしょうか。
理由は、主に3つあります。
理由1:対人関係を作るのが苦手
ASDの子は、
他の子と比べ想像力が弱い
という特性があります。
そのため、友達が言った冗談を
真剣に受け取ってしまい、
急に怒ったり反発したりすることがあります。
こういったことが続くと、
人間関係が上手くいきません。
悪化すると、クラスで孤立してしまうのです。
理由2:予定が変わるとパニックになる
前述したように、ASDの子は想像力が弱いです。
そのため、「予定が変わる可能性」を想定するのが苦手です。
その結果、次のような状態になります。
たとえば体育でサッカーをする予定だったのに、
雨で急に勉強に変わると、
パニックになってしまうことがあるのです。
このようなことが続くと、
学校に行くのが嫌になってしまいます。
理由3:特殊な環境が苦手
ASDの子は、
大きな音がする場所や、
人混みなどざわざわする場所が
苦手なことが多いです。
学校は集団で大きな音もするので、
行くだけでストレスを感じます。
これらの理由から、ASDの特性がある子どもは、
不登校になりやすいと言われています。
では、もし不登校になってしまったら、
どのように解決すればいいのでしょうか。
友達関係のトラブルを解決!学校復帰への3つのステップ

ASDの子が不登校になった場合、
スムーズに学校復帰させる流れがあります。
ここでは、効果的な
3つのステップをお伝えしましょう。
ステップ1:気力の回復
不登校の子の多くは、
学校に行く気力を失っています。
そのため、まずは良好な親子関係をつくり、
気力を回復させましょう。
具体的には、お子さんの正常な要求を聞いたり、
好きな食事を作ったりします。
また、学校でのストレスを、
家庭でできる限り取り除きましょう。
ステップ2:登校ハードルを下げる
気力が出てきても、
いきなり教室に戻るのは難しいです。
そこで最初は、フリースクールや
登校支援室に行くことから始めましょう。
これらの場所は、学校よりもルールが緩く、
先生のサポートも手厚いです。
人間関係も、
うまくいくようにサポートしてもらえます。
ステップ3:トラブル解消
フリースクールなどに慣れてきたら、
少しずつ学校に戻していきましょう。
その際、もともと学校で起こっていた
人間関係のトラブルを解決する必要があります。
そこで、場面ごとのロールプレイを行い、
「こういう場面では、こう言うと嫌われる」
などを練習しましょう。
簡単なトレーニングは、自宅でもできます。
同年代の子がいないとできない練習は、
公認心理師の先生などに
ソーシャルスキルトレーニングをお願いしましょう。
この3つのステップを順番に行うことで、
お子さんの学校復帰が近づくでしょう。
不登校中の勉強はどうする?家庭学習の効果的な進め方

ASDの子が不登校になった場合、
学校を休んでいる期間の勉強は、
どのように進めていけばいいのでしょうか。
ここでは、4つのポイントをお伝えします。
これを意識して、進めてみてください。
最優先は良好な親子関係づくり
大前提として、気力が出ていない時期は、
無理に勉強させる必要はありません。
まずは家庭でリラックスできる環境を作り、
良好な親子関係を築くことが大切です。
気力が回復してから、
無理のない範囲で勉強をスタートしましょう。
短時間の勉強から始める
ASDの子は、ADHD(注意欠如・多動症)
を併発していることも多いです。
そのため、集中力が長時間続きません。
15分勉強したら10分ゲームなど、
短いリズムで進めることが効果的です。
興味のある教科から始める
ASDの子は、
好きな教科と嫌いな教科が極端にわかれます。
そのため、まずは興味のある教科から始めましょう。
その方が、ストレスがかからないからです。
問題のレベルも、
7割くらいは解ける程度から始めると、
やる気を維持できます。
肯定的な声かけ
ASDの子は、否定されることが苦手です。
そのため、「なんでここまでしかできないの」ではなく、
「ここまでできたんだね」
という声かけを心がけましょう。
肯定的な言葉をかけることで、
勉強への意欲も高まります。
これらの4つのポイントを意識することで、
お子さんの勉強も進むようになるでしょう。
ASD特性に配慮した支援法!親ができるサポート方法
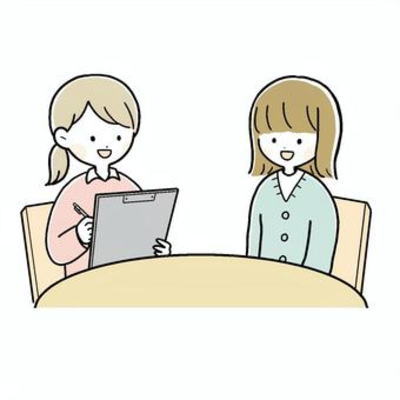
可能であれば、
不登校になる前に予防したいですよね。
そこで、日常生活の中で、
ASDの特性に配慮したサポートを
しましょう。
するとストレスが減るため、
不登校の予防につながります。
ここでは、3つの方法をお伝えします。
予定を事前に伝える
ASDの子は、急な予定の変更が苦手です。
そのため、変わる可能性があることは、
事前に伝えておきましょう。
たとえば「明日は体育だけど、
雨が降ったら保健体育に変わる可能性があるよ」
と伝えておくのです。
これで、突然の変更によって、
パニックになることがなくなります。
短所より長所を伸ばす
ASDの子は、苦手なことと
得意なことが極端にわかれます。
そこで、苦手なことを無理に直そうとせず、
得意なことを伸ばすようにしましょう。
興味のある分野ほど、能力を発揮できるからです。
将来、社会で活躍できる可能性も高まります。
専門家との連携
早い段階から、
専門家と連携しておきましょう。
何かあったときに、力になってくれるからです。
身近なところでは、
スクールカウンセラーがおすすめです。
公認心理師の資格を持つ先生なら、
発達障害の専門的な知識をもっています。
心療内科で、紹介してもらうのもいいです。
これらのサポートを行うことで、
お子さんが安心して学校生活を
送れるようになるでしょう。
【必読】良好な親子関係を作るためのテクニック
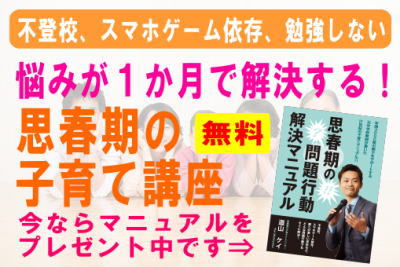
思春期は不登校だけでなく、
反抗的な態度やスマホゲーム依存、
友達トラブルや引きこもりなど、
多くの問題行動が起こりやすい時期です。
これらを改善するために必要なのが、
「良好な親子関係を築くこと」です。
その土台として、まずは
思春期の子どもの気持ちを理解
しましょう。
そこで現在、私が無料で配信している
「思春期の子育て講座」を読んでみてください。
以下の内容を詳しくお伝えしています。
- 思春期の子どもの気持ちと正しい接し方
- 子育てにイライラしなくなる方法
- 子どもとの会話が3倍に増えるテクニック
- 親に対する暴言や暴力の解決法
これらの内容は、
ASDの子育てにも役立つものばかりです。
適切な対応をすることで、親子の会話が増え、
子どもに笑顔が出てきます。
エネルギーや自信を取り戻し、
学校を前向きに考えられるようになるはずです。
今なら、3980円で販売していた
「思春期の問題行動解決マニュアル」を
受講特典としてプレゼントしています。
よろしければ、読んでみてください。
※のべ5万人以上が受講し、PTA講演会でも話している内容です。
動画で解説!!ASDの中学生の不登校対応策の詳細編