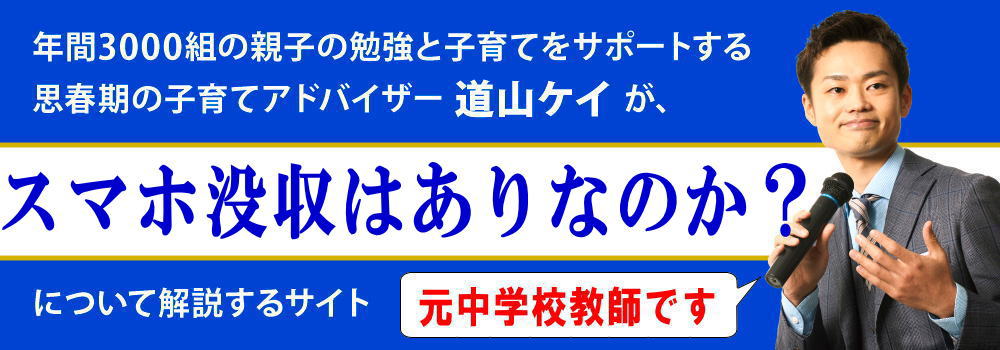子どもをスマホから離したい方へ
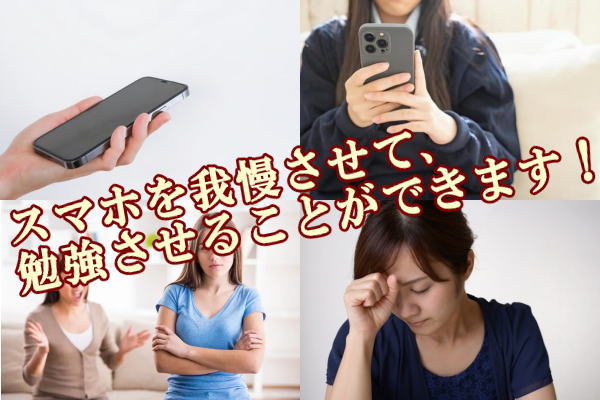
スマホ没収すべきか?に関するページ内容
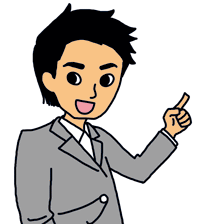
中学生のスマホ没収はアリかについて
解説します。
中学生の子どもがスマホの使い方で
問題を起こした時、
没収という手段を考える
親御さんは多いでしょう。
実はこれ、
やり方を間違えると危険です!
スマホ没収のデメリットと
効果的な代替案について
元教師の経験からまとめました。
適切な方法で対応することで、
親子関係を悪化させずに
スマホの正しい使い方を教えることができるはずです。
目次

スマホ没収のデメリット!中学生に与える4つの悪影響
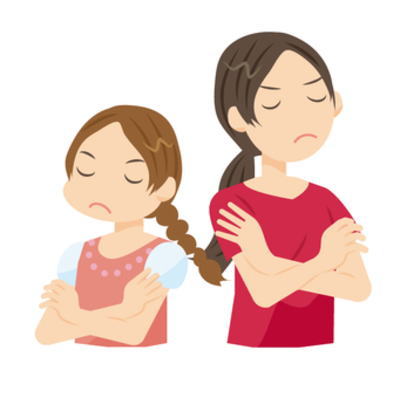
中学生のお子さんが、
スマホやゲームばかりしていると、
取り上げたくなりますよね。
しかし、9割のケースでは、
スマホを勝手に
没収しない方がいいです。
なぜなら、次の4つの悪影響が、
起こる可能性があるからです。
親子関係が悪くなる
子どもは、いきなりスマホやゲームを
取り上げられると、
「なんでそんなことするの」
「私の気持ちを理解してくれない」
と感じるでしょう。
その結果、親に対して恨みのような感情を抱き、
親子関係が悪くなってしまいます。
これが最も大きな悪影響です。
自律性が育たなくなる
本来、子どもは自分で
「この時間は使おう」「ここは少し我慢しよう」
という判断ができるように育てる必要があります。
しかし、親が取り上げ続けていると、
子どもは指示がない限り、
どれだけ使ってもいいと思うようになります。
その結果、自分で気持ちを我慢する力(自律性)
が育たなくなってしまうのです。
友達関係がうまくいかなくなる
今は多くの中学生が、
オンラインゲームやLINEグループなどで、
友達とつながっています。
スマホを没収されると、
この輪に入れなくなり、
翌日の会話についていけなくなることがあります。
その結果、友達関係がうまくいかなくなり、
学校に行きたくない
という状況にもつながりかねません。
力で解決する思考がついてしまう
親が力でスマホを取り上げると、
子どもも同じような解決方法を学んでしまいます。
たとえば、親にスマホを取り上げられた子どもは、
「じゃあ俺も力で取り返そう」
と考えるようになることがあります。
その結果、物を壊したり暴れたりして、
解決しようとする行動につながることもあるのです。
このような理由から、基本的には
突然没収するのはやめた方がいいでしょう。
スマホを没収をしてもいい2つのケースと注意点

では、スマホを取り上げるのは、
絶対にNGなのか。
もちろん、そんなことはありません。
没収してもいい場合が、
2つあります。
元々ルールを決めている場合
たとえば「夜23時以降も使っていたら、
お父さんお母さんは没収するよ」
と事前に約束していたとします。
そして、子どももこのルールに、
同意していたとしましょう。
ここでルールを守れなかった場合は、
「没収するって言ったよね」
と伝えて取り上げてもいいです。
これは約束を破った結果なので、
親子関係への悪影響はありません。
あまりに依存がひどい場合
依存があまりにひどく、
このままだと子どもの体調悪化に
つながりそうな場合は、
没収せざるを得ないケースもあります。
ただし、この場合は子どもが確実に暴れるため、
専門家のサポートの元で没収した方が安全です。
基本的には、専門家に相談してから
行動に移すといいでしょう。
なお、このような依存がひどい場合でも、
没収しなくても解決する方法があります。
そのため、まずは次の章で
お伝えする方法を試してみましょう。
取り上げるよりも効果的!中学生に行う改善3ステップ

では、どのように
アプローチしていけばいいのでしょうか。
基本的には3つのステップが効果的です。
少し時間はかかりますが、
危険もなく改善できます。
ステップ1:良好な親子関係作り
まず、子どもを無理やり変えるのではなく、
きちんと話し合いができる
親子関係を作ることが大切です。
そのためには、
子どもが望んでいることを、
できる限り親がやってあげましょう。
たとえば、好きなご飯を作ったり、
話を聞いてあげたりすることです。
そうすると子どもは
「お父さんやお母さんは忙しい中で、
僕のお願いを聞いてくれるんだ」
と感じ、愛情が届いて関係がよくなります。
ステップ2:ルールを決める
関係が良くなってきたら、
いきなり取り上げるのではなく、
まずは改めてルールを決めましょう。
この時に親が一方的に決めても、子どもは守れません。
そのため最初の段階では、
子どもも「これだったら守れるかな」
と思えるルールを話し合って決めましょう。
ステップ3:守る練習をしていく
最初からルールを守れるわけではありません。
守れないこともあると思うので、
試行錯誤しながら
きちんと守れるようにしていきましょう。
もし守れなかったら、
「一時的に預かるよ」という話は
事前にしておいても構いません。
ただし、それを納得してもらえるかどうかは、
最初の親子関係が全てです。
きちんと聞いてもらえるような親子関係を
作っておくことが前提となります。
このように段階的に進めることで、
子どもは自分の力でスマホを
コントロールできるようになっていきます。
自律性をはぐくませるために親がすべきサポート

最終的には、子ども自身が
自分でやりたい気持ちを我慢して、
勉強や他のことができる力を
育てていかなければなりません。
この自分でコントロールする力のことを
自律性といいます。
この力を育てるには、大事なポイントが2つあります。
過干渉をやめる
過干渉とは、「あれしなさい、これしなさい」
と親がいろんな指示をしすぎることです。
これをすると、
子どもは指示がないと動けなくなってしまいます。
干渉は必要最低限にして、
子ども自身の意志でできるように
させましょう。
もちろん最初から完全に放任するのではなく、
少しずつ子どもに任せる部分を
増やしていくことが大切です。
叱るのではなくサポートをする
子どもがスマホを触りすぎている時に、
恐怖でコントロールしようとする方がいます。
しかし、これでは「お父さんが怖いから使わない」
という状態になってしまいます。
そうではなく、守れるルールを作りましょう。
もし守れなかったら「どうしたら守れるか」を
一緒に考えることがサポートです。
こうして、最終的に
自分の力でできるようにしていきましょう。
【必読】スマホ時間を勉強時間に変えたい方へ
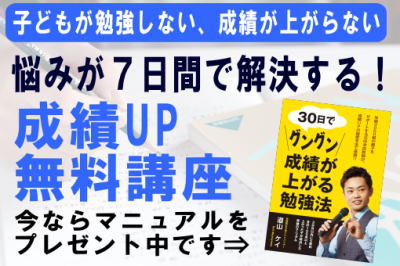
今回お伝えした方法を実践すれば、
子どものスマホ依存は改善していきます。
ただ、できることなら、
スマホ時間を、
勉強時間にしてほしいですよね?
そこで現在私は、
「7日間で成績UP無料講座」
を配信しています。ここでは、
- 成績を上げる方程式
- 半自動的にやる気が出る動機付け法(親向け)
- ストレス0で勉強量を増やす裏技
- 超効率的暗記テクニック
などを7日間で解説しています。
親子で読んでいただくと効果抜群です。
よかったらこちらも上手に利用して
効率良く成績を上げていただけると嬉しく思います!
※今なら3980円で販売していた成績UPマニュアルもプレゼント中です。
動画で解説!!スマホ没収はありなのか?の詳細編