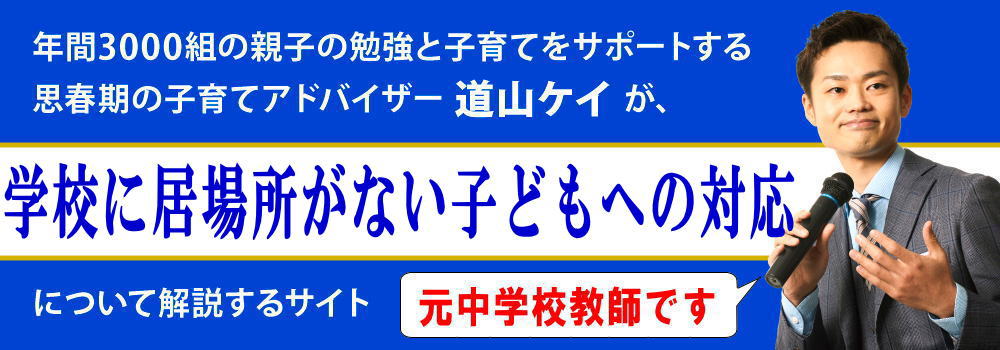子どもが不登校にならないか心配な方へ

学校に居場所がない子どもに関するページ内容
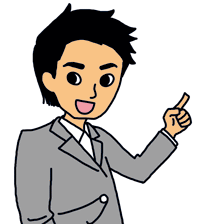
学校に居場所がない子どもへの支援法について
解説します。
学校でひとりぼっちになり、
心の中で「助けて」と叫んでいる
子どもたちがいます。
実はこれ、
一人で抱え込ませると危険です!
居場所がない子どもの孤独感を理解し、
脱出するための具体的な支援方法を
元教師の経験からまとめました。
適切なサポートをすることで、
子どもが安心できる居場所を見つけ
学校生活を楽しめるようになるはずです。
目次
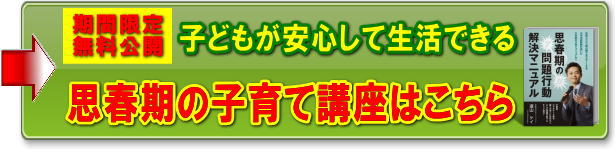
学校に居場所がない子どもが抱える3つの問題

学校に居場所がないと感じる子どもは、
多くの問題を抱えています。
大人が何もサポートしないと、
症状が酷くなります。
まずは、どのような問題が起こるかを、
確認してみましょう。
人間関係への恐怖
1つ目は、人間関係に恐怖心を持つことです。
居場所のなさは、
孤独感や不安感の原因になります。
人間関係がうまく作れないため、
クラスメイトに恐怖心を持ったり、
「誰も話しかけてくれない」
「嫌われているからいじめられるかも」
という不安を感じてしまうでしょう。
自己肯定感の低下
2つ目は、自己肯定感が下がることです。
人間関係がうまくいかないと、
「私はダメな人間だ」
「魅力がない人間だからこんな風になる」
と無意識で思ってしまいます。
その結果、さらに自信のない人間に
なってしまうのです。
勉強の気力低下
3つ目は、勉強への気力がなくなることです。
勉強は子どもにとって大変な作業なので、
友達関係や親子関係が
安定した状態でないと頑張れません。
居場所がなく孤独で
苦しい思いをしている子は、
勉強まで頑張る気力が出てこないのです。
これらの状態が続くと、
不登校から部屋に引きこもったり、
自己肯定感の低下でリストカットするなど
自傷行為に発展することもあります。注意が必要です。
「助けて」は危険?親が見逃してはいけない兆候とサイン

子どもから直接「居場所がない」と
相談されるケースは、まれです。
多くの場合、無言のサインを出してきます。
そのサインに早く気づくことが大切です。
ここでは、見逃してはいけない
危険なサインを4つお伝えしましょう。
苦しさの表現
1つ目は、苦しさを表現していることです。
たとえば、
「私は本当にいつも1人で、死にたい」
「なんでこんな生活になったんだろう。本当に辛い」
などのメッセージを
SNSやノートへ書いていることがあります。
このような辛い感情を出していたら、
危険な状態だと判断しましょう。
体調の変化
2つ目は、体調に変化が現れることです。
表情が暗くなったり、
明るい言葉や笑顔が減ったりします。
学校で、トラブルが起こっている可能性が
高いサインです。
生活リズムの乱れ
3つ目は、生活リズムが乱れることです。
寝る時間が遅くなったり、
朝起きられなくなったりします。
悩みがあると夜寝られなくなって、
朝も起きられなくなるからです。
会話の変化
4つ目は、会話の内容が変わることです。
昔は友達や学校の話題を話していたのに、
突然話さなくなったら注意しましょう。
人間関係が、うまくいっていない可能性があります。
このようなサインが出てきたら、
注意深く子どもの様子をチェックしましょう。
同時に、子どもの居場所作りを
行っていくことも大切です。
孤独から脱出する3つの方法!新しい居場所の見つけ方

では、新たな居場所は、
どのように作っていけばいいのでしょうか。
ここでは子どもの居場所を作るための、
具体的な方法を3つ紹介します。
学校の先生に相談する
1つ目は、担任や学年主任の先生に相談することです。
先生がうまく働きかけることで、
居場所ができることもあるからです。
たとえば、その子と仲良くなれそうな子に話をして、
みんなで会話する場を作ったり、
自然にグループに入れるように
サポートしてもらったりすることができるでしょう。
先生の働きかけで問題が解決することもあるので、
まずは相談してみることが大切です。
私も教師時代、休み時間は、
孤独で悩んでいた2人の子と
一緒に過ごすようにしていました。
すると、気づいたときには、
その2人が仲良しになっていました。
習い事に参加する
2つ目は、習い事への参加です。
学校のクラスが偶然合わずに、
孤独になることもあります。
習い事なら、
同じものに興味を持つ子が集まっているため、
仲良くなりやすいでしょう。
できれば週に1回は行けて、
家から近い場所を選ぶといいです。
習い事の後に、プライベートで遊びやすくなります。
学校や環境を変える
3つ目は、学校や環境を変えることです。
クラスにも習い事にも居場所がない場合、
フリースクールや適応支援室に行くことを
提案してみましょう。
専門の支援や理解あるスタッフが、
子どもの居場所作りをサポートしてくれるからです。
また、思い切って転校することも1つの方法です。
新しい学校なら1からスタートが切れるので、
居場所作りがうまくいきやすくなります。
以上が、新たな居場所作りに大切な3つの視点です。
子どもの状況に合わせて、
提案するといいでしょう。
子どもの孤独感を紛らわすために親ができる3つのサポート

子どもの居場所作りと並行して、
親ができるサポートも重要です。
次の3つを行うことで、
子どもは安心して
自分を出せる場が増えていきます。
自宅を安心できる空間にする
1つ目は、とにかく自宅を
安心できる空間にすることです。
子どもにとって学校は、
サバンナに放り出されたような
辛い場所になっています。
自宅が安心できる場所でないと、子どもは休めません。
そのため、お父さんお母さんは
笑顔を意識して過ごしたり、
「頑張れ頑張れ」
とプレッシャーをかけないように心がけましょう。
心の辛さを吐き出させる
2つ目は、心の辛さを吐き出させることです。
人間は辛さを吐き出さないと、
気持ちが楽になりません。
どんどん話を聞いて、
その気持ちに共感してあげましょう。
たとえば「学校で私ずっと1人なんだよ」
と言われたら、
「そうか、1人だと辛いよね。
本当に悲しくなっちゃうよね」
と共感してあげることです。
孤独感が、楽になります。
親が友達代わりになる
3つ目は、親が友達代わりになることです。
すぐに友達ができるわけではないので、
その間は親がサポートしましょう。
一緒にショッピングモールに行ったり、
一緒にゲームをしたりするなど、
子どもがやりたいと言っていることを
やってあげるだけで気持ちが楽になります。
自分の居場所ができるまでは、
親が友達の代わりになってあげることが大切です。
このように、子どもの気持ちに寄り添いながら
一緒に過ごすことで、子どもは安心感を感じ、
自分らしさを取り戻すことができます。
【必読】子どもの本音がわからない方へ
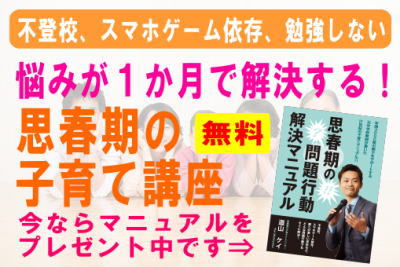
今回お伝えした内容を実践することで、
子どもの孤独は和らぎます。
安心できる居場所を見つけられるでしょう。
ただし、
「子どもがなかなか本音を話してくれない」
「部屋に引きこもっていて会話がない」
という悩みもあると思います。
そんなときは、
現在私が無料で配信している
「思春期の子育て講座」を
参考にしていただければと思います。この講座では、
- 思春期の子どもの気持ちと正しい接し方
- 心の辛さを吐き出させる具体的なテクニック
- 自宅を安心できる空間にする方法
- 子どもとの会話が3倍に増える方法
これらの内容について、
より具体的にお伝えしています。
読んでいただくことで、
子どものストレスや不安な気持ちを
ケアできるようになり、
居場所作りもスムーズに進むでしょう。
今なら3980円で販売していた
「思春期の問題行動解決マニュアル」を
受講特典としてプレゼントしています。
ぜひ参考にしていただければと思います。
※PTA講演会でも話している内容で、多くの親御さんに支持されています。
動画で解説!!学校に居場所がない子どもとその親への詳細編